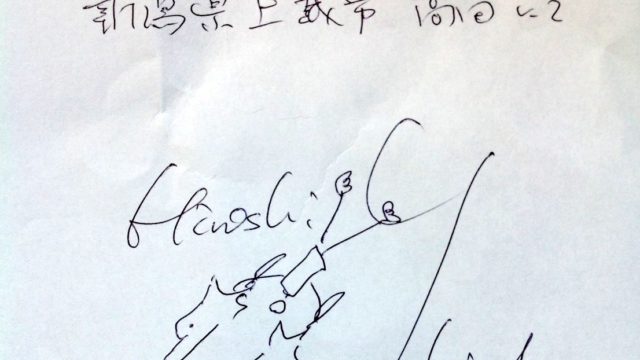五日目の午後にようやく雨が上がり、二階のバルコニーに出るとすぐ目の前で椰子の新緑の葉が風に揺れていた。しばらく眺めていると、その葉に二羽の小鳥が止まった。体はすずめほどの大きさで、色は半分が真っ赤で後の半分が真っ黒。細いクチバシで花の蜜を吸いに来るミツスイだった。その二羽は仲良く美しい声で鳴きながら毛繕いをしていた。バルコニーの下を見下ろすと大雨のあとに穴から這い出してくると言われているカニを、現地人が大きな袋を持って拾い集めていた。
しばらくして部屋に戻り、昼寝をした後、冷えたコーヒーをすすりながら窓越しに再び外に目をやると、先ほどのミツスイの数が増えているのに気づいた。そしてその右側の、大きな椰子の、葉のうなだれた茎の所に、更に茶色と白の別の鳥達が止まっているのが見えた。私はすぐさま部屋に戻り「鳥が海岸に戻ってきている。このまま海が穏やかになる証拠だ!明日は海に出よう‼︎」とカメラマンに告げた。
夕方二人でホテルの桟橋近くにあるバーに出かけた。未だ南西からの風で荒れている海を見ながら、最初にコロナビールを一杯やりジントニックを飲んでから、褐色のウエイトレスにクラムチャウダーの大盛りとフィッシュアンドチップスとパスタを一皿注文した。それら全てを平らげた後、部屋に戻って地元の新聞に目を通し、更にウイスキーソーダを二杯ほど飲んで床に着いた。しかしその夜は中々寝つかれなかった。ストームの影響でフライトがキャンセルになり、来るはずのツーリスト達が何日もグアムで足止めになっているのがやけに気になっていた。
翌朝、私は賛美歌の歌声で目が覚めた。既に感謝祭が終わり十二月に入ったのでクリスマスの準備の為に、環礁外の離島からキリスト教の様々な宗派の人たちが本島のホテルに集まって来ていた。カメラマンは既に起きていて、やはりカメラの手入れをしながら窓越しに「雨雲が多すぎる!陽が差さないと難しいんだ、沈船は…。」とひとり呟いていた。私は気の乗らなさげなカメラマンを説得してダイニングに出かけ、コーヒーとトースト、それにベーコンと半熟のボイルドエッグとハッシュブラウンポテトを口にほうり込んで、ホテルの敷地内にあるダイブショップに出かけた。しかし、そこには嵐のせいか数人のスタッフしかいなかった。その中に知り合いのナミがいたので声をかけた。これまた気が乗らなそうなナミに$20のチップを渡し、船を出してもらうことにした。そして我々はどんよりと低く垂れ込めた雨雲の下、トラック環礁の海底に沈む沈船を目指したのだった。
海底三十四メートルの深さに全長百三十五メートルの船が横たわっている。船首(BOW)に向かって、右側のほぼ中央の船底近くに魚雷が一発命中し、沈んだものと思われる。その傷跡の穴は水面から潜行して行った場合、通常目にすることはない。船の名は富士川丸という。
この季節から海の青さが変わり始める。暑い八月の濃い青から、貿易風のさざ波によるキラキラと青白く輝く美しい青へと変貌していく。今は澄みきった環礁内を見られる季節でもある。十二月半ばくらいから三月までの環礁内の透明度が著しく増す時期は、潜行すれば真下に横たわるその船を一瞬にして見ることができる。その姿は全く無傷のまま沈んだように思える程である。全形を留めた沈船の美しさは、目を見張るものがある。以前はマストが水面から二メートル程突き出していたのだが、ある時、酒に酔った現地人が船の操縦を誤り、マストに激突して折ってしまったらしい。たいへん残念でならない。
全景の美しさ、船首の美しさ、回遊魚(バラクーダ、ギンガメアジ、ロウニンアジ、カスミアジ、ナポレオン、ツンブリ、イソマグロ)の多さ、幻想的なエンジンルーム、まるで時間が止まったかのようなメモリアルプレート寄りの回廊・船尾(STERN)の下にある大きなスクリュー、下から見上げて見える数千匹のスズメダイに覆われた突き出た船首…。何もかもがこの一隻の沈船には凝縮されているように感じる。何度潜っても潜り飽きない船である。
我々は船の中央にあるブリッジにアンカーを打ち、ボートを固定して準備に取りかかった。事前にカメラマンとは船の上で撮影場所の順番を決め、お互い見える位置をキープしながら進もうということになった。先にカメラマンが入り私がカメラを渡し、三台のカメラで撮影する手はずだ。私もすぐにタンクを担いで潜行し、アンカーを打ったブリッジでカメラマンに追いついた。そこで一旦「止まれ!」の合図を出し、最初の撮影場所を指差し、マスク越しにもう一度サインを送った。すぐにカメラマンの目は私をとらえ、大きくうなずいた。そして再びOKサインを出し、水深十八メートルの船のほぼ中央に位置しているメモリアルプレートに向かった。そこには英語でこのように記されてある。
「1944年2月17日に沈む。」と…。
その後、我々は船尾方向に向かいデッキの回廊に入った。回廊の天井にはダイバー達の泡が張り付き、多くのソフトコーラルや色鮮やかなウミウチワがゆらゆらと揺れていた。ゆっくりと進んで行くと、船倉の中から出てきた数匹のコバルトブルーのカスミアジが、目の前を通り過ぎて行く。そこは外から遮断された空間であり、とても幻想的で、静止した六十年前の時を思わせる雰囲気をかもし出していた。
我々はデッキを抜け、次にマストに向かった。しばらく進むと大きな十字架状のマストが前に立ちはだかった。マストの左側には数百匹のギンガメアジの群れが渦巻いていた。その先で大きなマダラトビエイが飛び去って行くのが見えた。やがて船尾に着き、そこを回りこんで更に水深三十メートルにあるスクリューを撮影しに行った。スクリューの下は一面の白い砂地で、そこにも、まるで絨毯でも敷き詰めたかのようにぎっしりとギンガメアジが群れていた。その後更に海底三十二メートル地点まで行き、船の下をくぐり抜け、そのまま回りこみながらデッキの二十三メートル地点まで斜めにゆっくりと浮上した。それから船倉に入りエンジンルームに向かったが、陽が差しこんで来ないので、中はどんよりと薄暗かった。この条件では撮影は無理なので中央のやぐらの下を通り抜け、船首に向かう。
比較的浅くなっている船首では三十匹ほどのカスミアジの群れがいて、どうゆうわけかその中に一匹のナポレオンがいた。船首の先では青と黄色のたくさんのウミイロモドキの群れが大きく揺れていた。そこから船首の下に回りこんで、沈船に群れる数千匹のスズメダイを船首と重ねてシルエットで撮影。その後、再びアンカーを打ってあるブリッジまで戻って来た。
悪天候で気がせいているせいか、我々はかなりの速さで船を一周してしまっていた。エアーは未だ半分近く残っていたので、私はそのまま一台のカメラを抱えて、ブリッジの下水深二十メートルのデッキの上に留まった。カメラマンは水深十メートルくらいの所まで浮上し、クラゲを食べているハタタテダイを撮影している。私はひっそりと静まり返った水中で、ひとりエアーを吐き出す音を聞きながら、ぼんやりとしていた。
低く垂れ込めた暗雲、全く陽の差さない水中の沈船、ストームによるフライトキャンセルでトラックに来られず、ダイビングの泡の如くに消えてしまった十五名のダイバー達…。いつしか私は船のデッキの上で妄想に取り付かれ、苛立ち、焦燥に駆られていた。
そしてうだれかかった私の心が、絶望感で満たされようとした瞬間…、背後からそっと私の肩に触れてくるものを感じた。私は一瞬サメではないかと恐る恐る、ゆっくりと後ろを振り向いた。するとそこには三メートルくらいもある一頭のバンドウイルカがたたずんでいたのである。やさしい目をしながら包み込むように私を見つめるその表情は、とても柔らかくてそして暖かかった。私がゆっくりと右手を差し出すとイルカもゆっくりと首を傾げ、その後首を上下に振り出した。まるで笑っているかのようだ。
私がもう一度右手を差し出しながらそっと歩み寄ると、イルカもゆっくりと近づいてきて、私の指とイルカの口との間隔が徐々に狭まり…。指がイルカの口に触れた瞬間、イルカはキュル、キュル、と鳴き出して、私の回りをぐるぐると旋回し始めた。うれしさのあまり無心でその光景を眺めていると、しばらく辺りを泳ぎ回ってから向きを変え、濃いブルーの中に消えてしまった。ところがそのイルカが、数十秒の後に、更に別の二頭を連れて現れたのである!そのあと同じことが三、四回に渡って繰り返され、結局私は十二頭のイルカ達と戯れることができたのである。その間、最初の一頭はずーっと私の近くにいて、手を差しのべるたびに体を大きく振って喜んでいた。
やがてイルカ達は濃いブルーの海の彼方に消えていった。イルカ達が立ち去った後、さっきまでの暗い気分がすっかり晴れていた。その時初めてイルカに癒されたことに気づいたのだった。そして私は水深二十メートルの沈船のデッキから満面の笑みをたたえて、無事浮上することができた。
私はこの一頭を、トラック環礁内で出逢った最初のイルカとして、また「私はアルパであり、オメガである。始めであり終わりである(ヨハネ黙示禄二十一章六節)」という聖書の一節にちなんで、名前をギリシャ語のアルパとした。私はこのイルカに、人間に近づこうとした勇気と、私自身を大きく包み込んでくれた愛を感じた。そしてこの一頭のイルカを通して、私自身が大自然の中で生きているのではなく、生かされている存在なんだ!ということを骨身に染みて実感した。
これが、私が8年前に最初に出逢ったイルカとの物語である。その後、数多くのイルカと出逢ったが、アルパを越えるイルカは未だにいない。
まさしく、「アルパ(始まり)」と言うのにふさわしい出逢いだった。